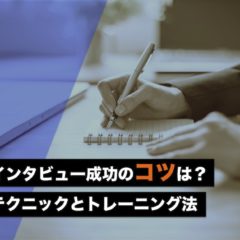句読点の打ち方―読点3つの鉄則と5つのワザ・句点4つのルール
( 最終更新日:2023年12月26日)
文章の途中に打つのが読点「、」、最後に打つのが句点「。」です。特に読点「、」については、「つい打ちすぎてしまう」「しかしどうやって打つかなんて習ったことも考えたこともない」、そんな方もいらっしゃるでしょう。
ライターさんの文章を直す機会の多い我々編集者としては、点の打ち方は文章の巧拙が如実に表れる部分だと感じます。致命的なミスにはつながらないものの、うまいライターさんは句読点といった基本も外してこないんですよね。
ここでは、句読点の打ち方・使い方で困ったという方に向けて、
- 読点の打ち方で迷わないための〈3つの鉄則〉
- 読みやすさを上げるための読点〈5つのワザ〉
- 意外と知らない句点〈4つのルール〉
についてお伝えします。なおこの記事を書くにあたっては、読点に関して弊社の編集者がライターさんに送っているアドバイスを30〜40個くらい見返して参考にしたほか、「あなたのライターキャリア講座」の内容の一部を引用しています。
打ちすぎず、打たなすぎず。読点「、」と句点「。」で文章のリズムを操りましょう。
どっちがどっち?句点「。」/読点「、」/句読点「。と、」
本題に入る前に、まずは句点、読点、句読点の違いを整理しましょう。
- 句点(くてん):「。」の符号。文の終わりを示します。
- 読点(とうてん):「、」の符号。文章の意味上・構造上あるいはリズム的区切りを示します。
- 句読点(くとうてん):句点「。」と読点「、」を合わせた呼び名です。
余談ですが、「。」と「、」のどっちが句点でどっちが読点だっけ?と混乱する読者も多いのではないでしょうか。
例えば、
- 句点:句の字の中に丸がある→「。」だ
- 読点:読んでいる途中の点だ→「、」だ
と覚えるのはいかがでしょう。ちょっと無理がありますかね。
読点「、」の打ち方〈3つの鉄則〉
読点で迷っている方を見ていると、読点が少なすぎるというよりは、読点を打ちすぎる傾向にあるようです。読点が多いとつっかえてしまって読みづらく、記事のリズムを損ねてしまいます。
- NG例 せっかくの誕生日、お子様と、一緒に、ケーキなど、いかがでしょうか?
- OK例 せっかくの誕生日、お子様と一緒にケーキなどいかがでしょうか?
一方、少ないは少ないでメリハリがないですね。
- NG例 駆け出しのライターではありますが依頼主から信頼されるようがんばります。
- OK例 駆け出しのライターではありますが、依頼主から信頼されるようがんばります。
ということで、打ちすぎてしまう、または打たないで書いてしまう方に向けて、読点の打ち方を以下〈3つの鉄則〉に集約してお教えします。
〈鉄則1〉一文を短く区切る
読点が多くなる原因の多くが、そもそも一文が長すぎるという問題。文章が間延びして読みづらくなり、必然的に読点の数も増えてきます。
一文一義(ひとつの文章にひとつの意味)を意識し、一文を意識的に区切ると読みやすくなるでしょう。文章を書き慣れていない方はえてして一文が長くなりがちです。また、一文を短くするとそもそも読点が不要になることも多いです。
【NG例】有名な小説『ロボ戦記』を読めば、人間のエゴに嫌気がさし、人間に従順でひたむきなロボたちに心を打たれ、人間が悪で、ロボットが善であると思わず叫びたくなる社会があるが、それは人間の幸せを人の手に委ねてはいないかと、自分自身に問わずにはいられない。
こちらのNG例は120文字ほどですが、その中に6つの読点があります。一文が長いので必然的に読点が多くなり、途切れ途切れで読みづらい印象を与えています。
【OK例】有名な小説『ロボ戦記』を読めば、人間のエゴに嫌気がさすだろう。人間に従順でひたむきなロボたちに心を打たれるに違いない。人間が悪でロボットが善である――思わずそう叫びたくなる社会がそこにはある。人間の幸せを人の手に委ねてはいないか?と問わずにはいられない。
一文を30文字前後で区切りました。文章を区切る過程で、読点のほか文言も一部修正しています。するとどうでしょう、読点が最初の文を除いて無くなってしまったことがおわかりだと思います。一文を短くすると、そもそも読点が不要になるという好例です。
〈鉄則2〉音読して息継ぎするタイミングで点を打つ
次に「音読」です。声に出して読んで「息継ぎをするタイミング」で読点を入れてください。
音読は時間がかかるし気後れするのもわかります。ただ小学生の頃にやったようなはっきりした音読でなくても、軽く口の先で読み上げるだけでも構いません。また人によっては、自分で音読するのではなく音声読み上げソフトに読ませ、自分は聞くことでチェックするという方もいるようです。Wordなど身近なソフトにも読み上げ機能はついていますよ。
「お子様と、一緒に、ケーキなど、いかがでしょうか?」と細かく区切って音読する人はいないと思います。一息で読めるところには読点を入れません。加えて「学校を、休んだため」のように一続きの要素の途中に読点を入れないことにも注意しましょう。
〈鉄則3〉文章を見渡してごちゃついているところで区切る
最後に文章全体をみて、文字が並びすぎてごちゃごちゃしていると感じた箇所を探します。文字が詰まっていればいるほど、文章は読みづらくなります。特に以下のように漢字・ひらがな・カタカナが続いてしまったところは要注意です。
- NG例 季節柄半袖を着る機会が増えてきた。
- OK例 季節柄、半袖を着る機会が増えてきた。
NG例では「季節柄半袖」と続いてしまっており、どこまでが一つの単語なのか分かりづらくなってしまっています。漢字が続くとそれだけでうっとおしい感じがしますね。そこでOK例では「季節柄」と「半袖」との間に読点を入れました。これなら、どこで単語が途切れるのかは一目瞭然ですね。
- NG例 ここではきものをあずけてください。
- OK例 ここで、はきものをあずけてください。
「ここで履き物を預けて下さい」とも「ここでは着物を預けて下さい」とも読めてしまいます。OKでは「ここで」の直後に読点を入れ、預けるのは「履物」であることを明確にしました。ご存知の通り「は」は単体の助詞とも他の品詞の一部とも読めてしまうので、区切りを示すために読点を使うことがあります。とはいえ、ここなら漢字を入れてあげた方が親切ですよね。
- OK例2 ここで履き物を預けてください。
以上、3つの鉄則をご紹介しました。このように、
- まず一文を短くして
- 次に音感(リズム)で区切って
- 最後に視覚的で区切る
という手順を踏めば、適切に読点を打てるようになるでしょう。
読みやすさ改善のために!読点〈5つのワザ〉
ここでは、読点をより効果的に用いて、「読みやすさを上げるために読点をどのように活用するか?」という観点から5つのワザ(効果的な使い方)を紹介します。
NG例、OK例を併記しました。読点の位置によって印象や意味合いが変わってくることに気付くでしょう。
〈ワザ1〉長めの主語を際立たせる
- NG例 現地の古い言葉で大草原を表す「パンパ」と呼ばれる肥沃な大地が広がるアルゼンチンは南米にある。
- OK例 現地の古い言葉で大草原を表す「パンパ」と呼ばれる肥沃な大地が広がるアルゼンチンは、南米にある。
主語の切れ目をはっきりさせて、アルゼンチンが南米にあることが分かりやすくなりました。
ただこの場合も、そもそも一文が長いのでいくつか区切った方が良さそうです。
- OK例2 アルゼンチンは南米にある国の一つ。ここには、「パンパ」と呼ばれる肥沃な大地が広がる。「パンパ」とは現地の古い言葉で大草原を表す。
〈ワザ2〉原因と結果の関係を明確にする
- NG例 学校を、休んだためテストを受けられなかった。
- OK例 学校を休んだため、テストを受けられなかった。
NG例では「学校を」の直後に読点が打たれていますが、「学校を休んだ」までがワンセットですので、ここで区切るのは不自然です。OK例では「学校を休んだため」の直後に読点を入れました。こうすることで、「学校を休んだ」という原因と「テストを受けられなかった」という結果が明確になりました。
ただ、この場合はそもそも一文が短いので読点なしでも違和感がないですね。入れないで済むなら入れない方がすっきりするでしょう。
- OK例2 学校を休んだためテストを受けられなかった。
〈ワザ3〉逆説の内容を分かりやすくする
- NG例 彼は、急いで駅に向かったが間に合わなかった。
- OK例 彼は急いで駅に向かったが、間に合わなかった。
NG例では「彼は」の直後に読点が来ていますが、逆説の助詞「が」の後ろに読点を打った方が、反対の意味合いが強調されて読みやすくなります。OK例では「彼は急いで駅に向かったが」の直後に読点を入れています。急いで駅に向かったことと間に合わなかったこと、つまり予想される結果が得られなかったことを分かりやすく伝えています。
ただ、この場合も読点なしの方が読みやすそうですね。
- OK例2 彼は急いで駅に向かったが間に合わなかった。
〈ワザ4〉対等な関係の物事を並列させる
- NG例 花は、かわいらしく山も、壮大で川は、澄み切っていた。
- OK例 花はかわいらしく、山も壮大で、川は澄み切っていた。
NG例では花、山、川がそれぞれどうなっているのかが分かりづらいです。OK例では要素ごとに読点で区切り、花・山・川の情報をバランスよく並べています。先の「学校を休んだ」までがワンセットというのと近いですが、一続きの要素の途中に読点を入れると途端に読みにくくなります。
〈ワザ5〉直前の言葉が直後にかからないことを示す
- NG例 父は楽しそうにはしゃぐ孫を眺めていた。
- OK例 父は、楽しそうにはしゃぐ孫を眺めていた。
NG例の場合、楽しそうなのが父なのか、それとも孫なのかが分かりません。そこでOK例では、「父は」の直後に読点を入れました。こうすることで、「楽しそうにはしゃぐ孫」でひとくくりの意味だということが分かりやすくなります。
ここで練習問題!
「私は庭で花を持った女の人を見た。」という文章に読点を打った場合、「私が庭にいる」ことを明確にする読点の打ち方はどちらでしょうか。
ア)私は庭で、花を持った女の人を見た。
イ)私は、庭で花を持った女の人を見た。
※解答は記事末尾にあります。
句点「。」の打ち方
句点「。」については「文末に打つ」という明確なルールがあるので、そこまで迷う方もいないかと思います。ただ、記号やカッコ書きとの兼ね合いで一定のルールはあるので、以下の4つだけご紹介しておきましょう。
〈ルール1〉文末に注釈として丸カッコ()を入れるときには、丸カッコの後に句点を打つ
- NG例 「あなたのライターキャリア講座」のスタンダードコースでは、毎週決まった曜日に講義を行います。(祝日を除く)
- OK例 「あなたのライターキャリア講座」のスタンダードコースでは、毎週決まった曜日に講義を行います(祝日を除く)。
〈ルール2〉筆者名、出典などを丸カッコ()に入れて文末に添える場合は、丸カッコの前に句点を打つ
- NG例 「あなたのライターキャリア講座」には大変満足しています(田中さん)。
- OK例 「あなたのライターキャリア講座」には大変満足しています。(田中さん)
〈ルール3〉!や?で終わるときには句点を打たない
- NG例 「あなたのライターキャリア講座」に不足はないのか?。
- OK例 「あなたのライターキャリア講座」に不足はないのか?
〈ルール4〉「」の末尾には句点を打たない
- NG例 田中さんは「『あなたのライターキャリア講座』には大変満足している。」と語ってくれた。
- OK例 田中さんは「『あなたのライターキャリア講座』には大変満足している」と語ってくれた。
※上記、「句点「。」と読点「、」の決まりを知る | 日経クロステック(xTECH)」「知っているようで知らない!? 句読点「。」「、」の役割と付け⽅「20のルール」 : ビジネスとIT活用に役立つ情報」など参考にしております。特に日経クロステック様の記事にあったルールはほぼそのまま借用させていただきましたm(_ _)m
まとめ
句読点、特に読点の打ち方を中心に説明してきました。
ただ、ここで説明したのは教科書的な基本原則に過ぎません。「読点で文章のリズムを整える」とすると、次は「リズムとは何か」という話になります。ここは自分で感性を鍛えていくことになります。
それではどうやって鍛えるのか?ライターの近藤康太郎氏の書いた『三行で撃つ 〈善く、生きる〉ための文章塾』(CCCメディアハウス)にこのような一節があります。
落語、浪曲、講談、歌舞伎、短歌、俳句、講演、ヒップホップ……エクリチュールのリズムの教材は、パロールにあります。だからこそ、わたしたちは、説経節、歌舞伎に義太夫、狂歌に漫才も含め、語り芸といわれているものはすべて、勉強しなければならないんです。パロールの〈構造〉をまねして、エクリチュールの本質である静謐さに、移植するんです。
第17発「リズム感【3感・其の二】」より、太字は原著のまま
近藤氏はこの直後で、「感性とは、努力で鍛えられる天性」とも述べています。
幸い今の時代、こうした文芸に限りなく手が届きやすくなりました。Spotifyなどの音楽聞き放題サービスでは落語や講談なども楽しめます。図書館に行けば無料で貸し出ししてもらえますよね。
良い文章に触れることはもちろん、目や耳を使って話芸に触れてリズム感を伸ばしていく。それでやっと、読点「、」の打ち方が洗練されていくことでしょう。
〈おまけ1〉読点の魔力
あっきゃんさんが、「読点の魔力」と題して画像つきで読点の使い方を解説した投稿をしていました。こうして分かりやすく・見やすくまとめていただけるのはありがたいですね。
〈おまけ2〉読点「、」の打ち方の解説動画
解説したnoteはこちらです。余談ですがこちらの丘村さん、地道にライティングのノウハウをYouTubeやnoteで発信しており、私の注目するライターの一人です。
〈おまけ3〉コンマ「,」文化庁が見直し検討
1年半も前のものですが、この記事を書くにあたって情報収集する中でたまたま知ったニュースです。
民間ではひろくテン「、」で記載されていますが、中央省庁では昭和27年に発行された「公用文作成の要領」に従いコンマ「,」で書くようルール化されています。長らくそのルールは守られてきており、公文書のほか学校教科書でもコンマが使われてきました。私も小学校の書写の時間に、「横書きではコンマを使う」と習ったのを覚えています。
そんな公文書のなかに使われているコンマ「,」について文化庁が見直しを検討しているようです。
参考サイト:公文書の「,」なぜ? 半世紀以上、見直し検討(2019.11.18)
※こちらのニュースは2019年のものなので、今では更に検討が加速しているかもしれませんね。
〈おまけ4〉ライティング講座を開講しております
当ブログを運営している株式会社YOSCAでは、プロライターの思考法を学べる「あなたのライターキャリア講座」を運営しております。

※練習問題の解答 ア)
編集協力:鎌田陽、阿部道浩
- E-E-A-Tを高める方法とは。SEO担当者必見のテクニック紹介 - 2024年1月18日
- 【500人に調査】おすすめライター講座13選と失敗しない選び方 - 2023年12月2日